
5: 08/21(金)21:23:59
今日のオススメ
【ニコ生の富士山滑落配信で謎の声が聞こえる】7:07「こっちに来ないでぇ…」10:07「こっち来い」10:32「 もどれ…」
・ 首都直下地震ってNHKも特集組んでるしそろそろなんじゃないの?
・ 前科者「何年も時給22円で労働して臭い飯食うのにも耐えて償ったぞ…」看守「外でも頑張るん やで」
江戸時代の江戸には水路が結構あった
みんな地下を通した水路から水を組み上げていた
そのため疫病が流行る時は早かった
というのは後世の風説らしい
太夫という位が早くになくなったからな
最高位の女を身請けするのに必要な金額は
だいたい7000万円くらい
大人ならほぼ必ず吸うし、妊婦も吸う。
タバコは健康を害するものではなく、むしろ健康によいとされていた。
タバコの葉だけでタール無いだろうから、
今の紙巻タバコよりは健康によかったんじゃね?
町人は武器を持てなかったので『喧嘩キセル』という
一メートルくらいあるキセルを護身用に持ってた
本気でやりあうと侍でも負けるような兵器だったとか
タン切れの薬だったんだっけか
参勤交代はあんなにゆっくり歩いてられないから全力疾走だった
「下に、下に」と言えるのは徳川親藩だけで他の藩は「下がれ、下がれ」と言ってた
しかも人々は脇道にそれるだけでよかった
一口に「江戸時代の貨幣価値に換算すると~」と言っても時代によって相当差がある
1両=60万円だった時もあれば、1万円もしなかった時もある
江戸時代のに換算してどうする
江戸幕府開闢から明治維新までの時間の方が遥かに長い
かなりの晩年まで裏名義のペンネームで春画描いてた
今の同人作家と同じ
かまどの灰も灰買いが買ってくれた
髪の毛を集める仕事があった
火鉢を使い始めて良い日が決まってた
砂糖は薬局で売買されてた
都市計画が微妙ではあったけど驚くほど早く拡大してゆくことができた
その日の生活費をその日に稼ぎ、一日で大抵使いきっていた
「宵越しの銭は持たない」というのはそれを表した負け惜しみ
みな今日の運勢を自宅で占うのが普通だったのだ。
それは来客ごとに使いまわして出すためで、食べるためのものではなかったため、
そういった暗黙の了解を知らない人がうっかり食べてしまうと、無粋なヤツとして家主に睨まれた
ちなみに、一週間ほどでカピカピになるので、そしたらやっと家主の腹におさまるのであった
その理由は、食べるときに音が大きく鳴るため
江戸っ子の間では、音のならない食べ物が粋として持て囃されていた
しかし、数の子は塩っ気があるため、飯がとにかくよく進んだ
そのため、来客にはあまり出されなかったと言われる
現在、下町と呼ばれている浅草や上野はお寺の街なので門前町
他に宿場町、港町、屋敷町などがある
他国から来た武士の身分は現地の平民より事実上低かった。
江戸でもめ事を起こせば最悪お取り潰しにもなりかねないため、
それを承知の江戸町民がチキンレース的に他国の武士をおちょくることもままあった。
裏浅葱とか田舎侍!って意味だしな…
特別厳しいのが箱根の関所というだけで(しかもそれも別にそんなに厳しくはない)、他の関所はほとんど総スルーで通れた
なので、町民のみならず子どもたちまでも伊勢参りにも行けたわけである
ちなみに取り調べを受けるときは、対象が女性だった場合はちゃんと女性の係員に取り調べさせた
丁稚奉公の子どもたちが、ある日パタッと集団でいなくなる場合がある
それは大抵伊勢参りに向かったもので、伊勢参りのために無断で行方不明になるのも
基本的に許されていた
また、犬が伊勢参りをするのも複数報告されている
伊勢参りをする犬は、首にカゴを着けている
そのカゴに道中の人々が食べ物などを差し入れるわけだ
勝海舟の親父で江戸最強説のある勝小吉も子供の頃に抜け参りをしている
のれんは客が帰り際に手を拭くために掛かってた
必ずしも綺麗な形に作れない田畑の収穫量の計算をはじめ、
「神社への奉納」という形での自作の計算問題がたびたび公開され、
そういうのがエスカレートして、今でいうネットの掲示板上で行われるような
クッソレベルの高い数学バトルが繰り広げられていた
それは将軍の行列のみで、他の大名に関してはやれ家の屋根に登って見物したり、茶屋でお茶を飲みながら見物したりと、それぞれ好き勝手な態勢でいた
また、行列の前に身を乗り出したとしても、いきなり切り捨て御免とはならず、一番前の武士に追い払われて終わるか、その前を走る露払いに排除されてお咎め無しであった
人相書きは似顔絵じゃなくて特徴を文章で書き記しただけのものだった
江戸時代の後期まで秋刀魚は人気がない魚だった
将軍は専用の特別な赤っぽい謎の酒しか飲めなかった
何故なら包丁で縦に切ると、徳川家の家紋に似た模様が現れるためである
へぇー
今でも博多の人は山笠の時期にキュウリは食べないらしいよ
理由は同じく、断面が串田神社の紋になるから
当時インドにあったアメリカ海軍東インド艦隊が派遣されたもの
「菜を上げる(名を上げる)」、「菜を残す(名を残す)」に引っ掛けた願掛けである
大名側でも少しでも経費削減しようと色々頑張っており、
江戸の国境までは最低限の人員でダッシュ、
そこからはエキストラを雇って何とか体裁を繕った。
なお、当然江戸から遠くなるほど旅費がかかるのだが、
逆に監視の目が届きにくくなるため薩摩などは密貿易でぼろ儲けしていたのでセーフ。
薩摩藩はすげぇ貧乏だったよ
密貿易程度のはした金ではとてもまかないきれないくらい負債がでかかった
片手にフグを持った友人が、一杯やろうと家を訪ねてくる
それを断れるのは、基本的に女房持ちに限定されていた
女房持ち以外の者が断ると、臆病者扱いを受けることになる
それだけは江戸っ子として、なんとか避けたかった
そして、今日もまた人死にが出るわけである
切腹が形骸化して単なる打ち首であったために素早く終わった
現代に於いて古事記は読めない。
当時、古事記は解読不能だった。それを約35年掛けて解読した
江戸に瓦屋根が広まったのは棒れん坊将軍が瓦葺き禁止令を廃止し、瓦葺きを奨励する助成金制度をつくったから
幕末に越後の川上という家が尊王志士に肩入れしたために勝海舟と縁ができたのだが、
そこの長男が「欧米と渡り合うには日本もワインが無くてはならん」
という勝の勧めで、本格的な国産ワイン醸造を始めることになる。
多大な苦労の後、「日本ワインの父」と呼ばれるほどの功績を残し、
その事業は「岩の原葡萄園」が今日まで受け継いでいる。
船の上では操船どころか船酔いはひどいわ威張るわ知識はないわで大変お荷物だったそうだ
臨海丸とは……咸臨丸ではないのか
近藤勇は楠木正成を尊敬していたが、楠木正成が出来たという理由だけで、
拳を口に突っ込んだり出したりする一発芸を繰り返し繰り返し練習していた
間違えた☆テヘッ
緩衝材として使われていた
今日のオススメ
・ 別れさせ屋の女に復習した話
・ コメダ珈琲のシロノワールプリンで泣き崩れる大人が続出
17歳上の姉ちゃん「私ね…実はあなたのお母さんなの」俺「は???」
・ 毎日ストロングゼロ飲んでる奴がビビリまくる画像
【富士山滑落事故】47歳ニコ生主、塩原徹さんの半生が明かされる
・ 【閲覧注意】ガチの怪奇現象がTwitterに投稿される
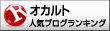
オカルトランキング
・ TOPに戻り他の記事を読む
ライター及び編集:mana : 2019/12/06 edit
画像https://publicdomainq.net/ 元スレ http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1440159695/

コメント
コメント一覧
江戸の中期~後期にかけて、細い眉が大流行し、いなせな男性は先を争って眉を抜いたり剃ったりしていたらしいです
さらに銭湯(沐浴場)には、「脱毛用の泥袋」が置いてあり、アカスリのように産毛を泥袋で擦って脱毛していた
お前ら江戸時代でもモテないじゃんwww